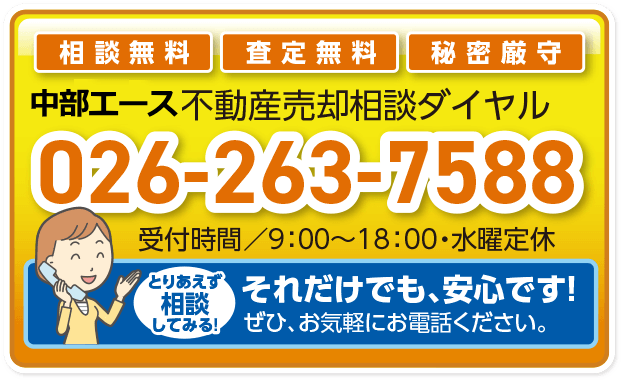「不動産を相続したけれど、名義変更はまだ…」
そんなまま放置していませんか?
これまでは相続登記に明確な期限はなく、義務ではないとされていましたが、
2024年4月1日から法改正により義務化され、3年以内の申請が必要になりました。
この記事では、相続登記の義務化の背景、具体的な期限や罰則、放置によるリスクなどを、60代・70代の方にもやさしく、丁寧にご紹介します。
なぜ相続登記が義務化されたのか?
相続登記の義務化は、全国的に増え続けている「所有者不明土地問題」に対応するためです。
背景にある社会的課題
- 登記されずに放置された土地の増加
- 公共事業・防災計画・空き家対策などが進まない
- 相続人の代替わりで権利関係が複雑化
このままでは地域の再生や災害対策にも支障をきたすため、法律が改正されました。
相続登記の義務と期限について
いつから義務化されたの?
2024年4月1日から、不動産登記法が改正され、
相続人は「相続または遺贈によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行う義務があります。
過去の相続も対象になる?
はい、2024年4月1日より前の相続であっても、まだ登記をしていない場合は義務の対象となります。
2024年4月1日時点で未登記の不動産は、
2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。
期限を過ぎたらどうなる?罰則はあるの?
正当な理由なく登記を怠った場合、過料(罰金)が科される可能性があります。
罰則の内容
- 10万円以下の過料(行政上の罰)
- 相続人ごとに課される可能性あり
- 法務局からの催告後も応じなかった場合に対象
「知らなかった」では通用しない時代に変わりつつあります。
相続登記を放置することのリスクとは?
相続登記を先延ばしにすると、次のようなリスクがあります。
① 権利関係が複雑になる
- 複数の相続が重なる「二次相続」
- 孫・甥・姪まで相続が進む「代襲相続」
登記が進んでいないと、誰が権利者なのか特定できなくなることもあります。
② 売却・担保・活用が一切できない
不動産の名義が被相続人(故人)のままだと、
- 売却ができない
- リフォーム費用のローンなども組めない
- 担保に入れて借入することも不可
せっかくの資産が「使えない土地」になってしまいます。
③ 書類や戸籍が入手困難になる
相続から年月が経つと、
- 被相続人の戸籍が廃棄される
- 住民票の除票が取得できない
こうなると登記に必要な書類が揃わず、手続きが困難になる場合もあります。
間に合わない場合の対処策
① 正当な理由があれば過料は免除される
以下のような事情がある場合、罰則が免除される可能性があります。
- 相続人が重病・高齢・障害などで手続き困難
- 相続人同士で争いがあり、協議がまとまらない
- 戸籍収集に時間がかかる
② 「相続人申告登記」で暫定的に対応
どうしても遺産分割が進まない場合は、
自分が相続人であることだけを登記する「相続人申告登記」で義務を果たすことが可能です。
正式な所有権移転は後日でもOK。
とにかく“期限内に手続き”することが重要です。
相続登記を進める際のチェックリスト
1. 必要書類を確認する
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 遺産分割協議書(協議が成立している場合)
- 不動産の登記事項証明書
2. 司法書士に相談する
不動産の名義変更は専門的な書類が多いため、
相続登記に慣れた司法書士への依頼が安心です。
3. 相続税の申告(10ヶ月以内)と合わせて進める
不動産を含む相続財産がある場合、
相続税の申告期限(相続発生から10か月)と合わせて登記を進めると効率的です。
まとめ|今後は「放置=リスク」。早めの対応を
- 2024年4月から相続登記が義務化
- 過去の相続も2027年3月末までに登記が必要
- 放置すると過料の対象になる可能性も
- 売却・活用・相続税申告にも影響が出る
相続登記は「資産を守るための第一歩」です。
不動産が関係する相続が発生したら、まずは登記の準備に着手しましょう。
相続登記のご相談は中部エースへ
中部エースでは、長野市を中心に相続不動産の名義変更・売却相談を多数お受けしています。
✅ 空き家・相続トラブルの解決実績あり
✅ LINE・Zoom・訪問でのご相談対応OK
「自分のケースでも義務化の対象になるのか不安…」
そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。